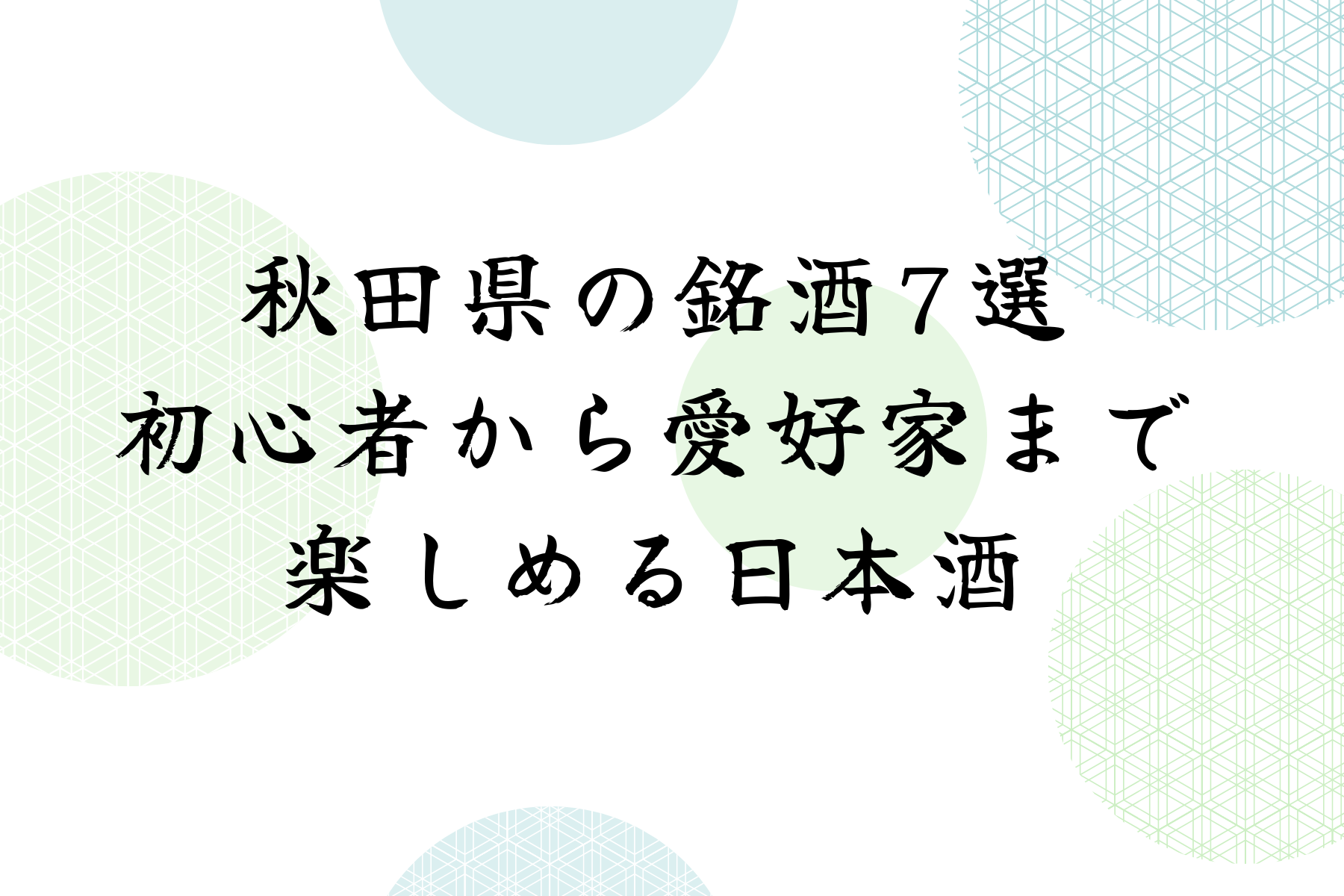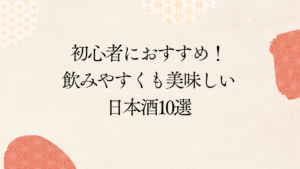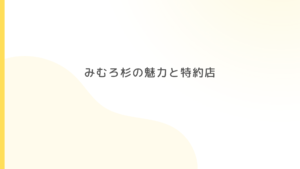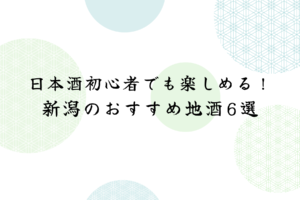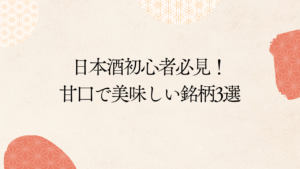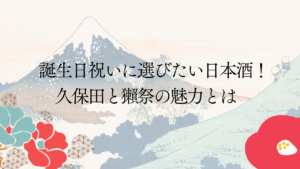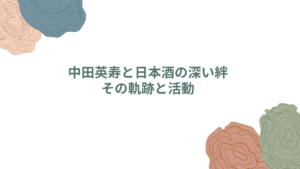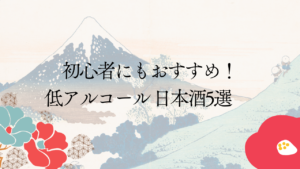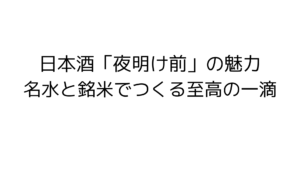秋田県の日本酒は、オール秋田産の技術を活かして美味しい酒を醸し出すこともできる一方で、各蔵がそれぞれの哲学に基づいた酒造りを行うことで、独自の魅力を持っています。地元で栽培される「秋田酒こまち」や「美郷錦」といった酒米を使用し、秋田県発祥の酵母と、清らかで軟水質の仕込み水によって造られる日本酒は、まろやかで上品な口当たりを実現し、秋田ならではの個性を存分に感じさせてくれます。
秋田県発祥の酵母
6号酵母
6号酵母は、日本酒醸造において重要な役割を果たす酵母の一つで、昭和5年(1930年)に新政酒造で発見されました。日本醸造協会から頒布されている酵母の中で最も古いものであり、日本酒酵母の歴史の礎となっています。
6号酵母の最大の特徴は、発酵力の強さと低温でも高い活性を発揮する能力です。そのため、寒冷地の秋田県においても安定した高級酒造りが可能となり、旨味のある酒質を実現しています。また、香りは穏やかで澄んだ印象を持ち、派手さよりも品のある香味を提供する点で、酒蔵が個性を引き出す際に最適な酵母と言えます。
新政酒造では、この6号酵母を全ての銘柄に使用しており、「新政酵母」としても知られています。穏やかな香味と強い発酵力を持つ6号酵母は、多くの酒蔵で使用され続けています。
秋田流花酵母AK-1
秋田流花酵母AK-1は、1991年に秋田県で開発された清酒酵母で、秋田の日本酒の個性を象徴する存在です。この酵母は、りんごや梨、パイナップルを思わせる甘酸っぱくみずみずしい香りを特徴とし、爽やかで軽快なタイプの日本酒を生み出します。その味わいは雅で華やかであり、日本酒に上品な魅力を与える要素として高く評価されています。
平成8年(1996年)には協会酵母15号(泡なし1501号)として正式に登録され、広く利用されるようになりました。デビュー当時、AK-1は非常に高い評価を受け、特に秋田を代表する名杜氏、高橋藤一氏が全国の品評会で「金賞」を獲得した際に使用したことで、その実力が広く知られるようになりました。
秋田県の代表的な酒蔵と銘酒
齋彌酒造店:雪の茅舎
雪の茅舎は、自家培養酵母を使用しています。製造過程では「三ない造り」を採用しており、櫂入れをしない、濾過をしない、加水をしないという自然の力を最大限に生かした独特の製法を貫いています。
その味わいは、深みがありながら透明感も兼ね備えており、適度な酸味とコク、そして旨味が特徴です。その品質は多くの受賞歴からも裏付けられており、全国新酒鑑評会では金賞を19回も受賞しています。
雪の茅舎は、自然の力を活かした製法と職人の卓越した技術が見事に調和した日本酒ブランドとして、秋田県を代表する存在となっています。
新政酒造:No6
新政酒造は、秋田県産米のみを使用し、伝統と革新が融合した酒造りを行う蔵元として広く知られています。生酛純米造りを採用し、自然の力を生かした丁寧な製造工程が特徴です。また、新政酒造は「協会6号酵母」を発祥させた蔵元としても有名で、この酵母は現存する最古の清酒酵母として日本酒の歴史に深く刻まれています。
製造過程では、45本の木桶を使用した伝統的な仕込みが行われており、この手法により独特の風味と深みが引き出されています。代表的な銘柄として、「No.6 ナンバーシックス」、「Colors カラーズ」、そして「PRIVATE LAB プライベートラボ」が挙げられます。これらの銘柄は国内外で高い評価を受けており、いずれの銘柄も入手困難です。
秋田醸造:ゆきの美人
代表銘柄の「ゆきの美人」は、料理に合い、落ち着いて飲めるお酒を目指して造られています。その特徴は穏やかな香りとやわらかな口当たり、そしてすっと切れる後味の良さです。これにより、飲み飽きることなく料理とともに楽しめる日本酒として多くのファンに愛されています。
秋田醸造は「NEXT5」プロジェクトに参加していました。このプロジェクトは新政酒造も含む秋田県の5つの蔵元の若手経営者が集まり、技術交流や共同醸造、イベントの開催をなどの活動を行い、「次世代を見据えた酒造りを模索し、秋田の酒造りを牽引できるような存在になろう」という想いからNEXT5と命名しています。
小玉醸造:太平山
小玉醸造株式会社は、秋田県潟上市に拠点を構える、歴史と伝統を誇る日本酒・味噌・醤油の醸造元です。小玉醸造の代表銘柄である「太平山」(たいへいざん)は、秋田の名峰「太平山」にちなんで命名されたブランドです。この銘柄は、秋田流生酛造りの発祥の蔵としての伝統を引き継ぎ、深い味わいと品質の高さで多くの人々に愛されています。
全国新酒鑑評会での複数回の金賞受賞をはじめ、東北清酒鑑評会では優等賞や知事賞を受賞するなど、その品質が高く評価されています。これらの実績は、小玉醸造の伝統的な製法と高い技術力を象徴しています。
山本酒造店:山本
山本酒造店の代表銘柄には、「山本」があり、フレッシュな味わいが魅力です。この蔵では、秋田産の原料にこだわり、地元の米、水、酵母を使用して日本酒を製造しています。香りを抑え、食事に合う日本酒を目指した酒造りが特徴で、搾りたてのフレッシュな味わいを活かした商品展開を行っています。
また、山本酒造店は革新的な取り組みを積極的に行う蔵元としても知られています。本醸造や大吟醸の造りを廃止し、純米酒に特化することで、より純粋な味わいを追求しています。全国新酒鑑評会では秋田県産の原料のみで挑戦し、金賞を獲得するという快挙も成し遂げています。
経営方針としては、蔵元杜氏の山本友文氏が陣頭指揮を取り、杜氏制を廃止することで蔵人全員が主体的に酒造りに参加する体制を構築しています。山本酒造店は、「NEXT5」プロジェクトに参加していました。
両関酒造:花邑
両関酒造の酒造りの特徴として、秋田流長期低温発酵法を採用し、仕込み水には栗駒山系の名水百選に選ばれた「力水」を使用しています。代表的な銘柄には「花邑(はなむら)」や「翠玉(すいぎょく)」があり、どちらも国内外で高い評価を受けています。「花邑」ブランドは、その開発過程において、十四代を醸す高木酒造の高木顕統社長から技術指導を受けています。この指導は単なる助言にとどまらず、米の選定や醸造方法、品質管理といった酒造りの全工程にわたるものでした。こうした高木社長の指導により、「花邑」は十四代に近い味わいを持つ日本酒として注目を集めています。
木村酒造:福小町
木村酒造は、秋田県湯沢市に位置する、創業元和元年(1615年)の歴史ある日本酒蔵です。秋田県内で2番目に古い酒蔵とされ、豊臣家の重臣であった木村重成の一族によって創業されたと伝えられています。
代表銘柄の「福小町」は、その名の通り福々しい味わいと高い品質で、多くの日本酒ファンに親しまれています。この酒蔵では、400年の伝統を守りながら、地元の恵みを最大限に活かした酒造りを続けています。
受賞歴も輝かしく、2012年には「大吟醸・福小町」がIWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2012のSAKE部門で最高賞「チャンピオン・サケ」を受賞しました。さらに、「令和5年度 秋田県清酒品評会」において「大吟醸 福小町(山田錦)」が吟醸酒の部で「秋田県知事賞」を受賞するなど、その品質の高さは国内外で広く認められています。
まとめ:秋田県の銘酒6選:初心者から愛好家まで楽しめる日本酒
秋田県は、日本酒の奥深い世界を存分に楽しめる地域です。その豊富な銘柄や多彩な味わいは、初心者から上級者までを魅了します。次回の旅行や特別な日の一本として、ぜひ秋田の日本酒を選んでみてはいかがでしょうか?
Sake Café Journalでは、日本酒にまつわる幅広い情報をお届けしています。このブログでは、初心者の方にも楽しんでいただける基礎知識から、愛好家向けの専門的な内容まで、さまざまな視点で日本酒の魅力を発信しています。もしこの記事に興味を持っていただけましたら、ぜひ他の記事ものぞいてみてください。きっと新しい発見があるはずです!